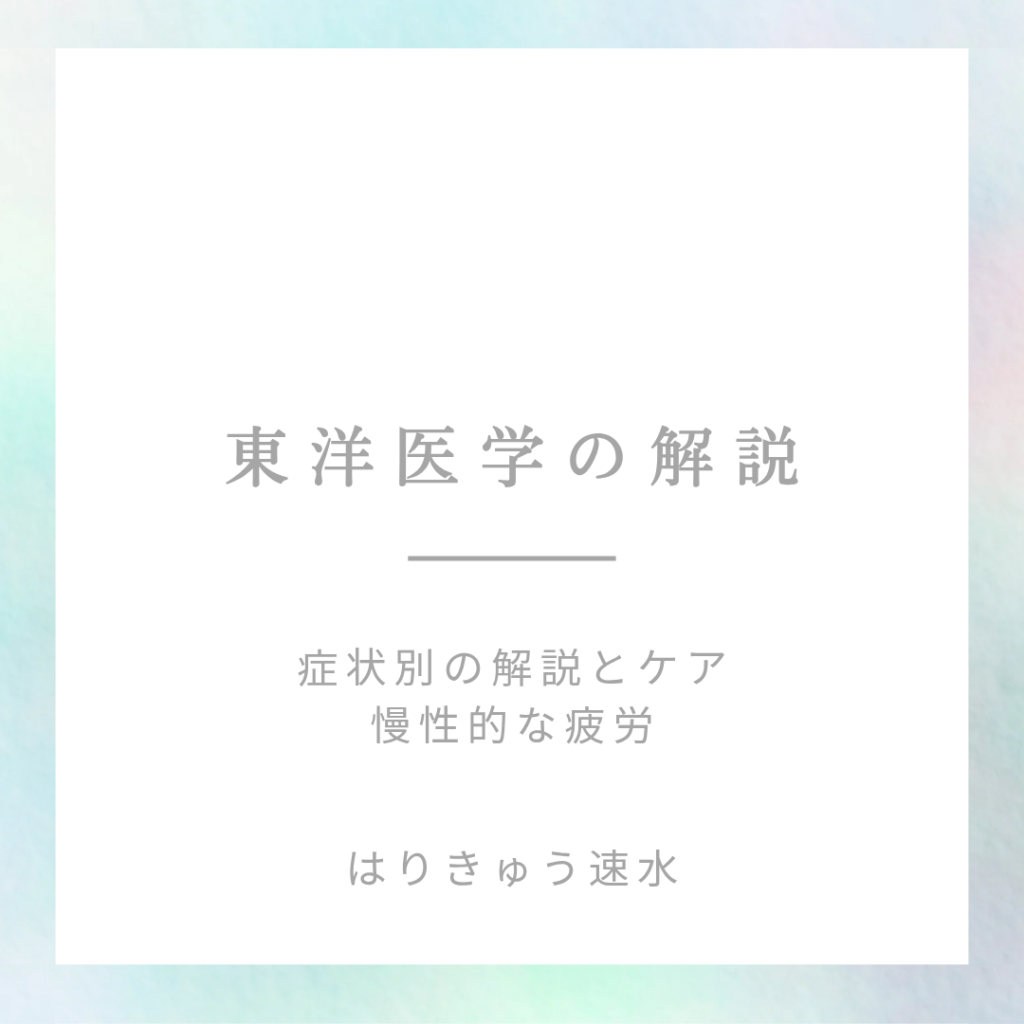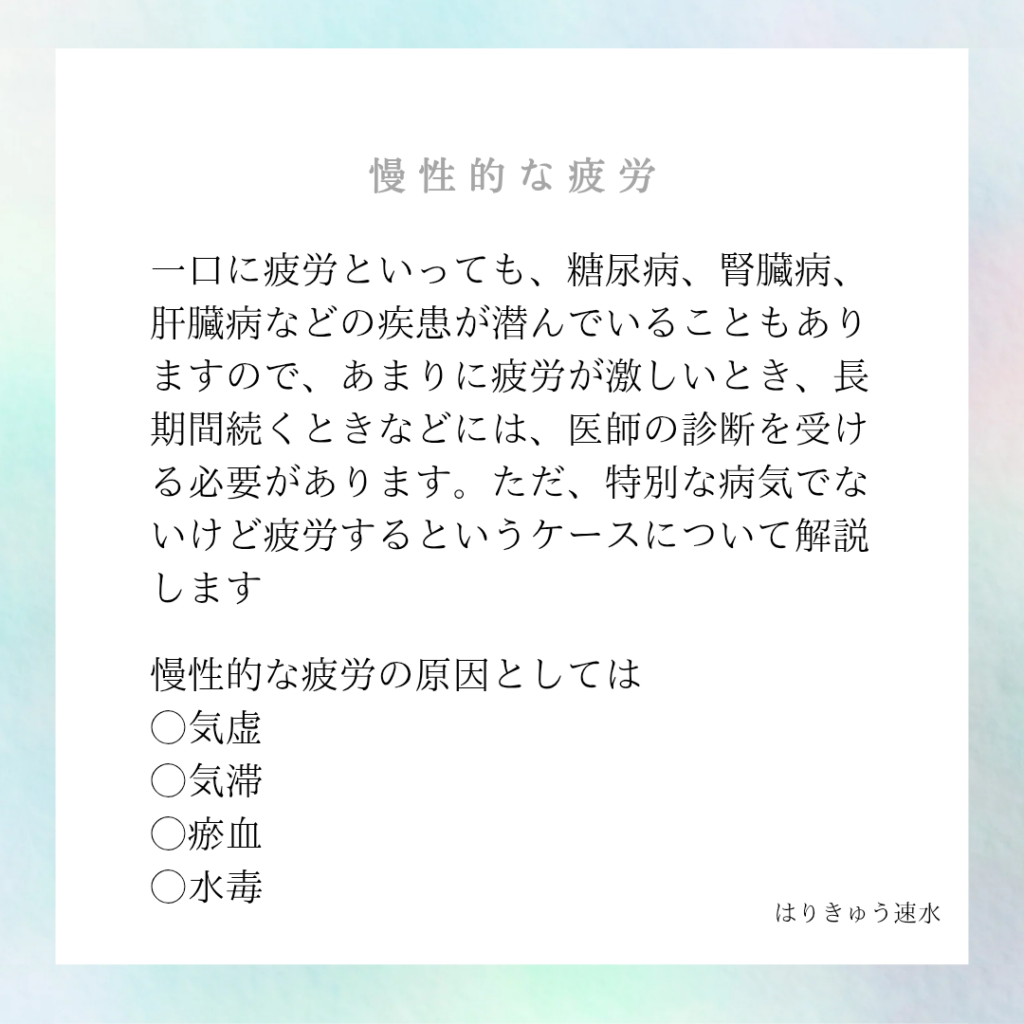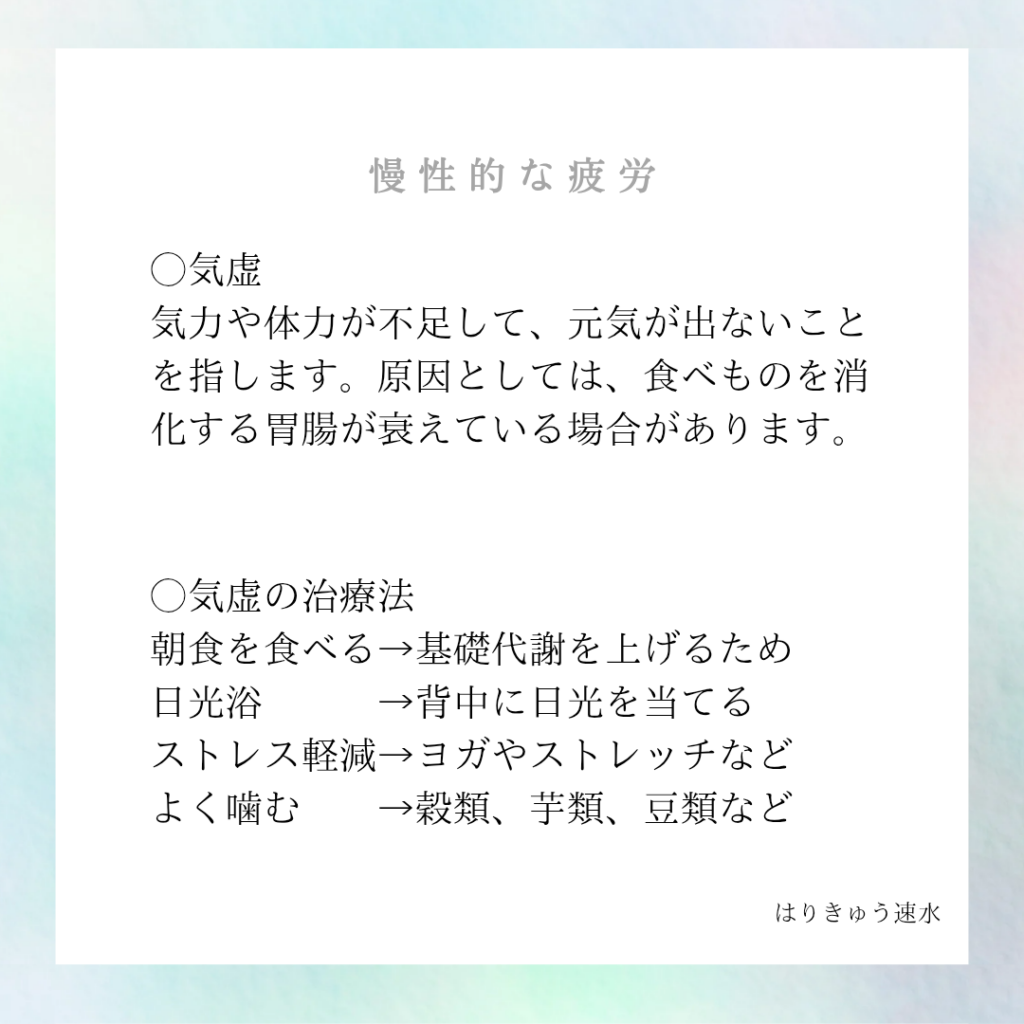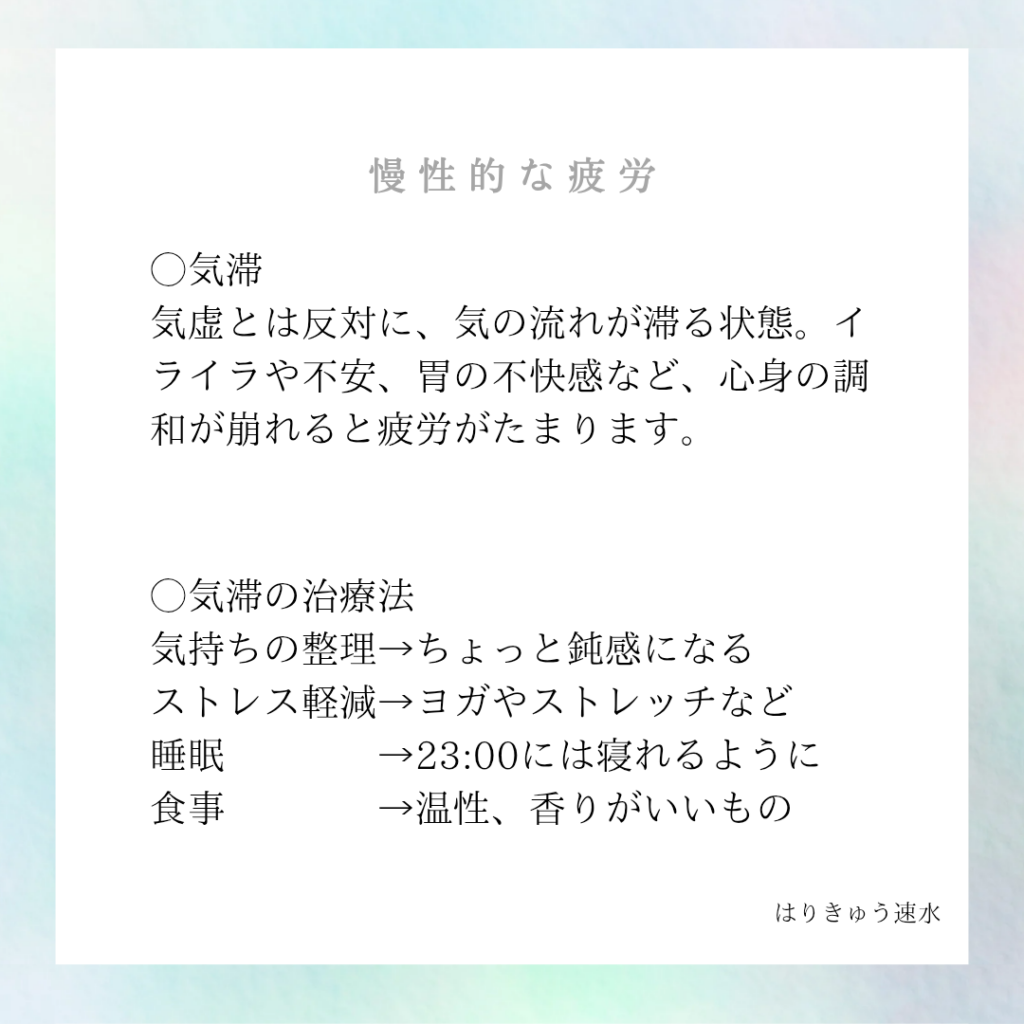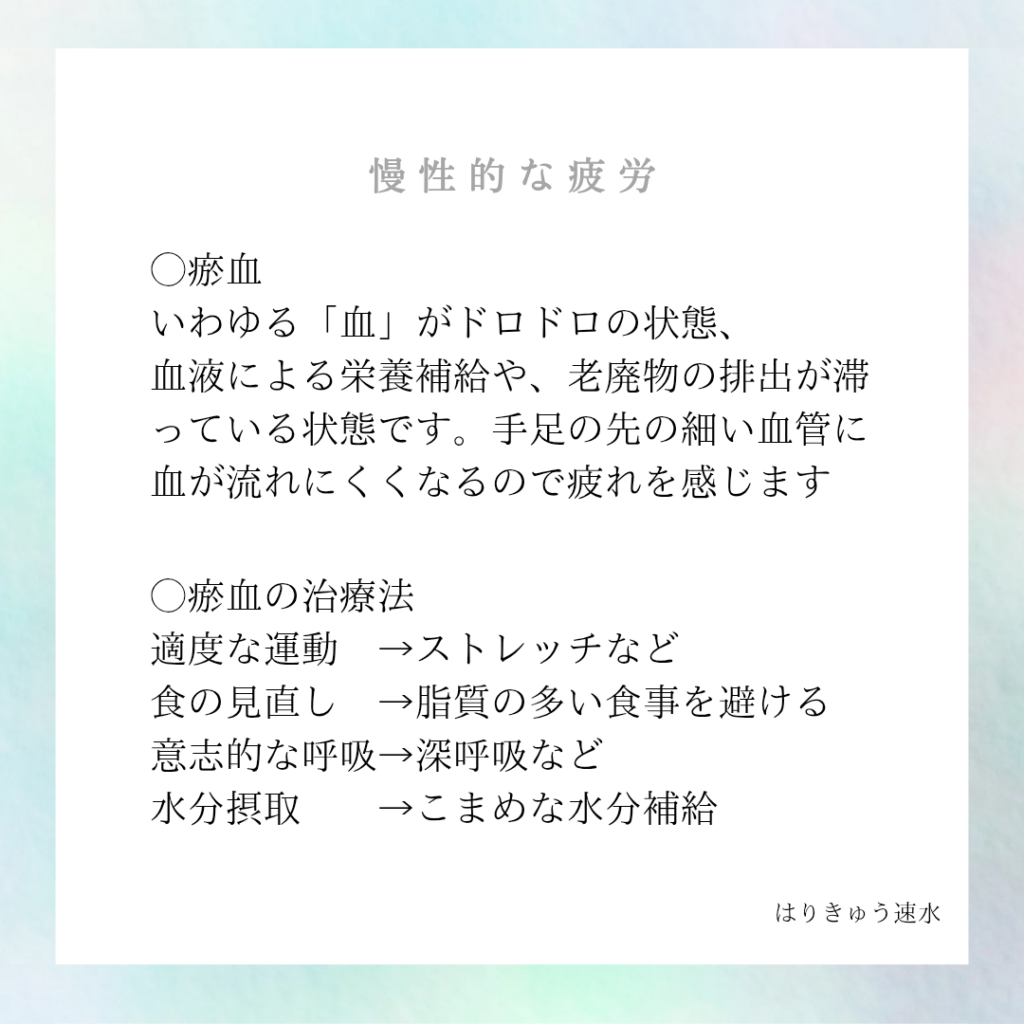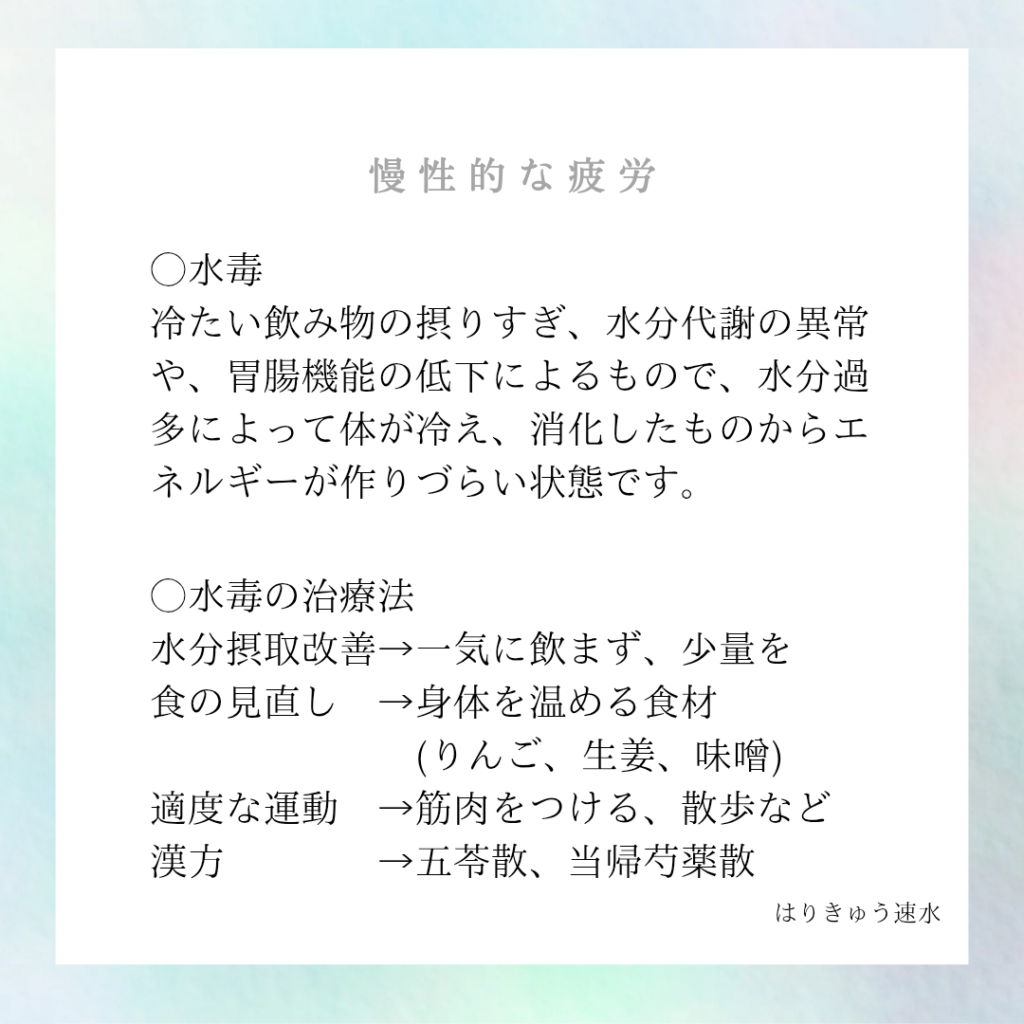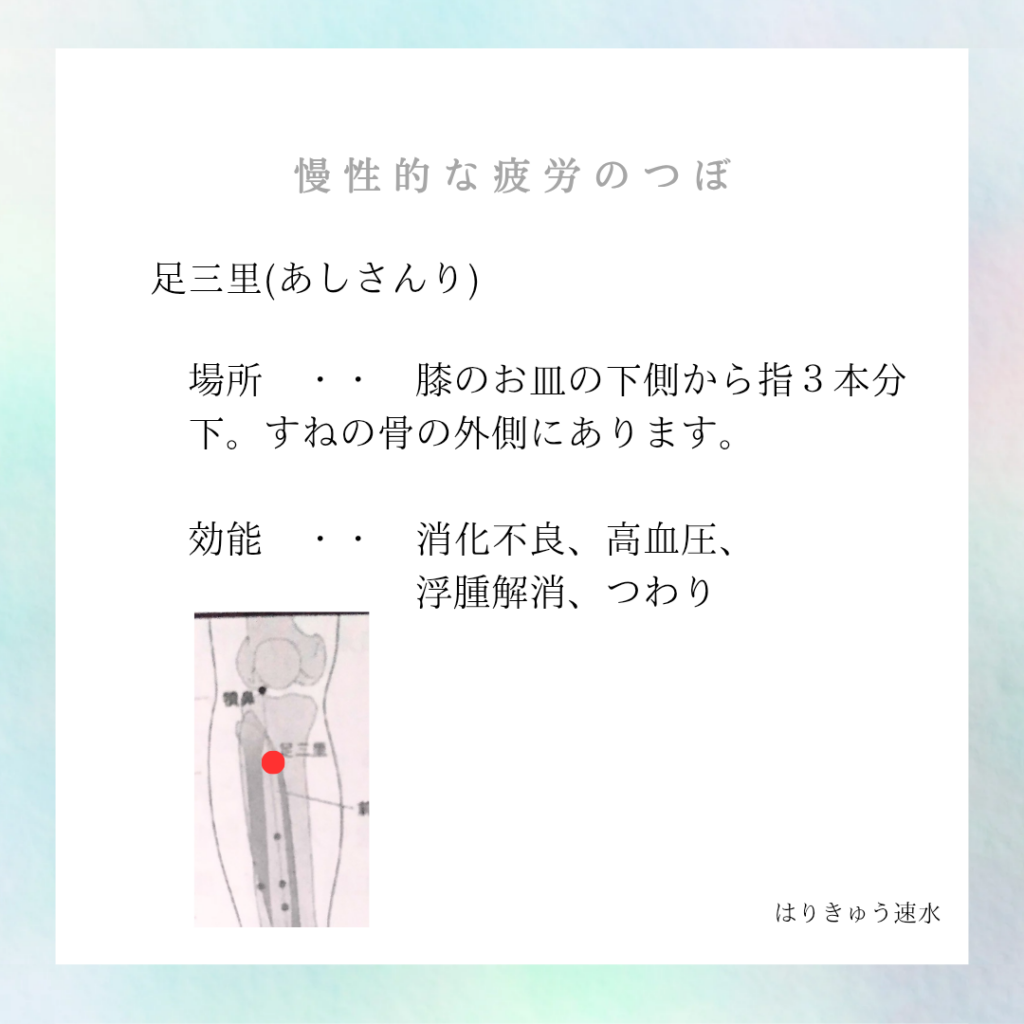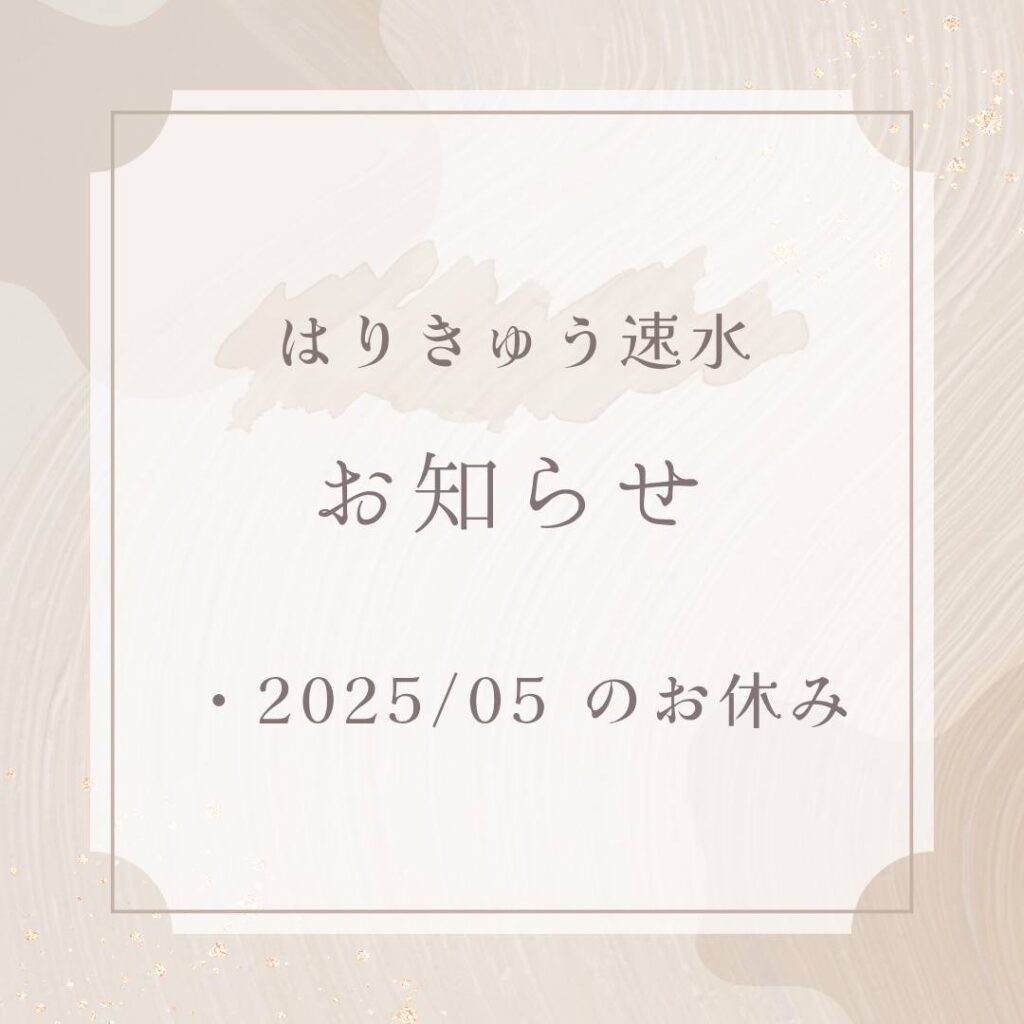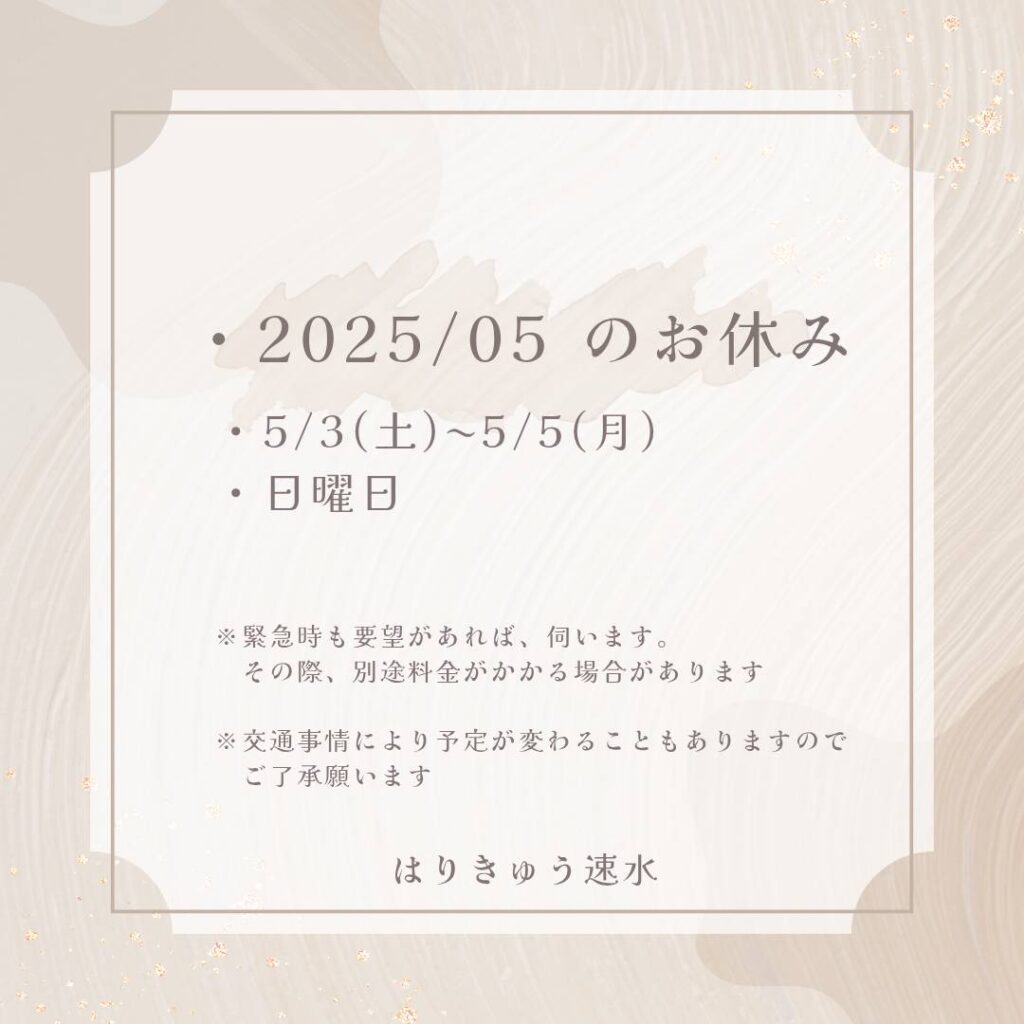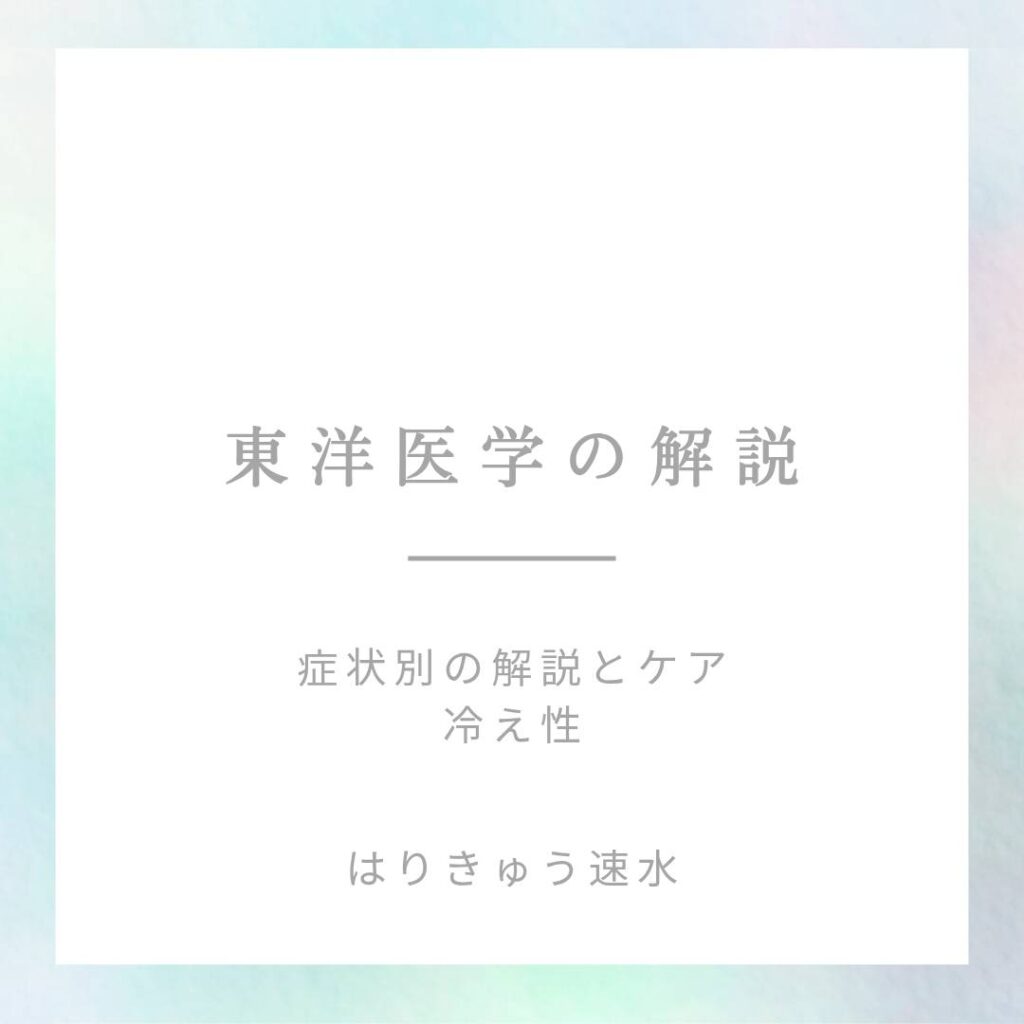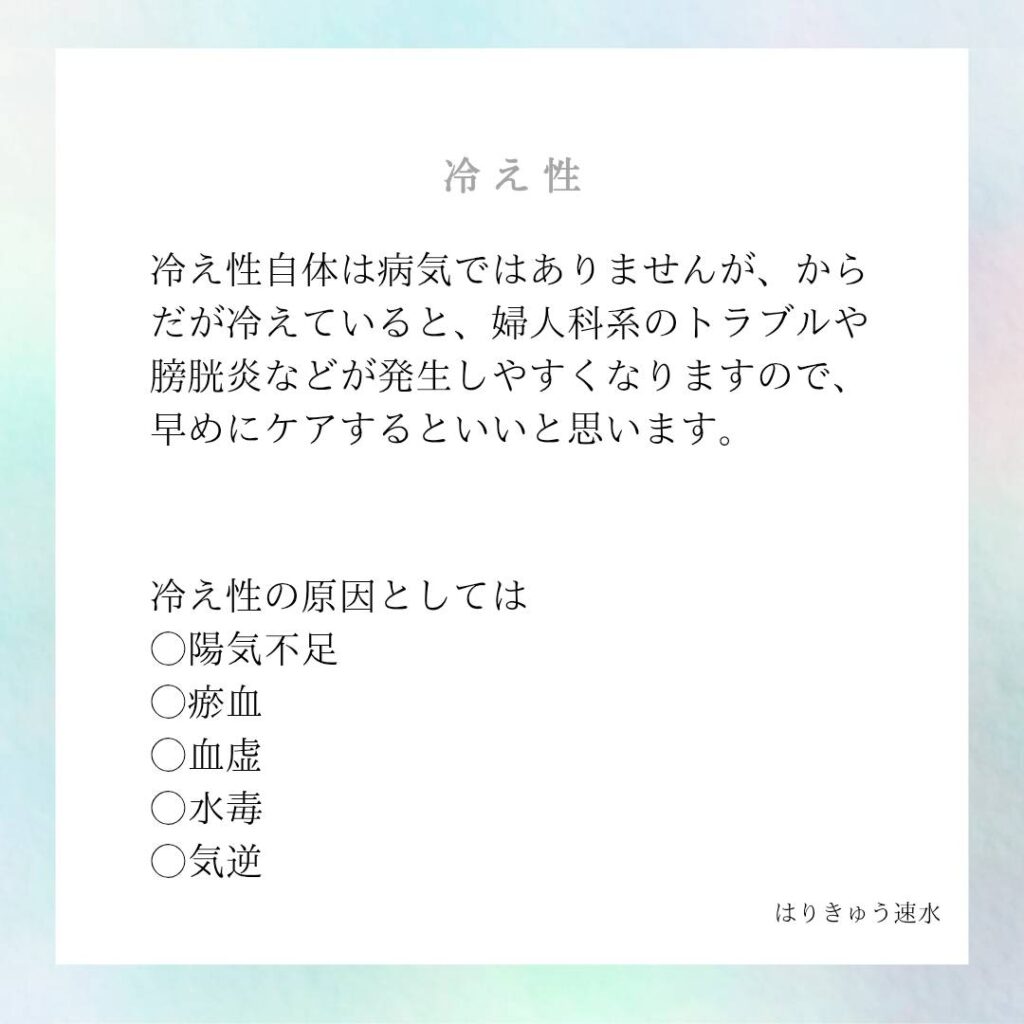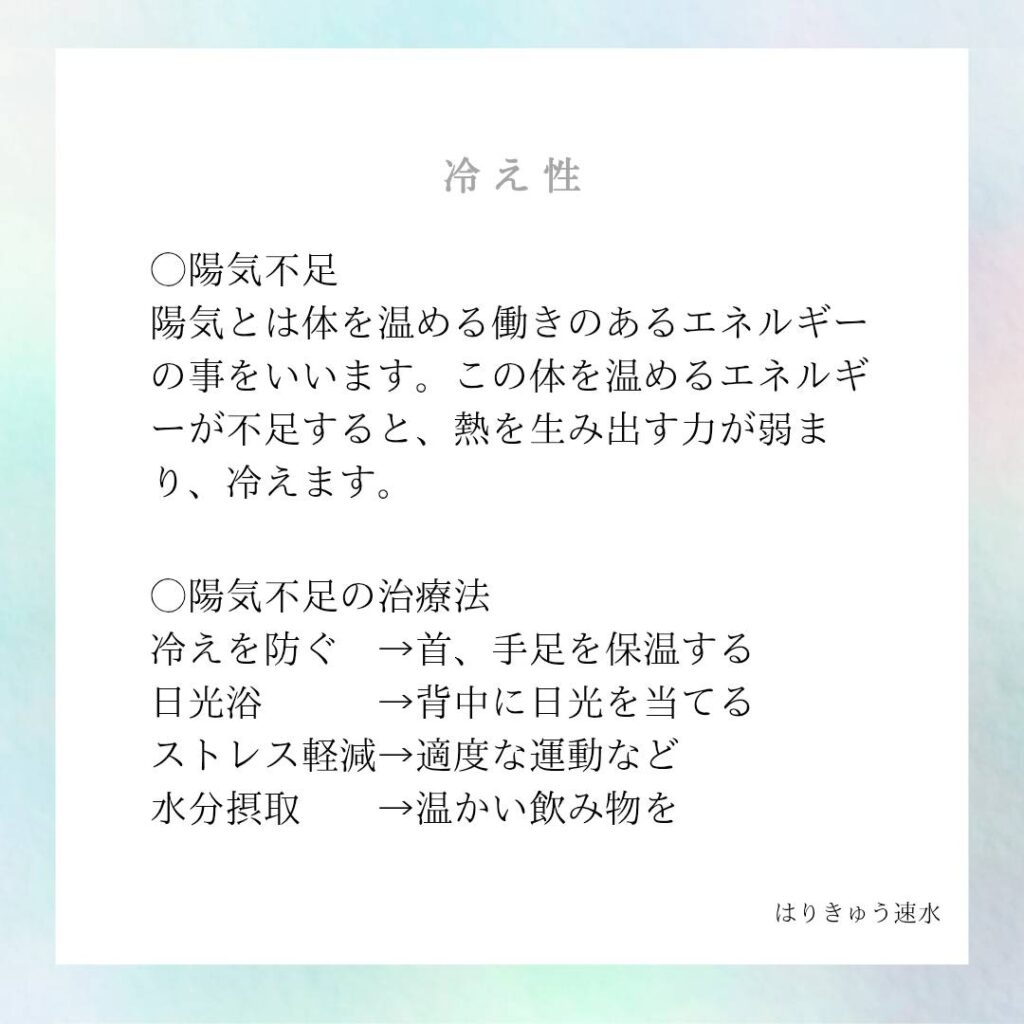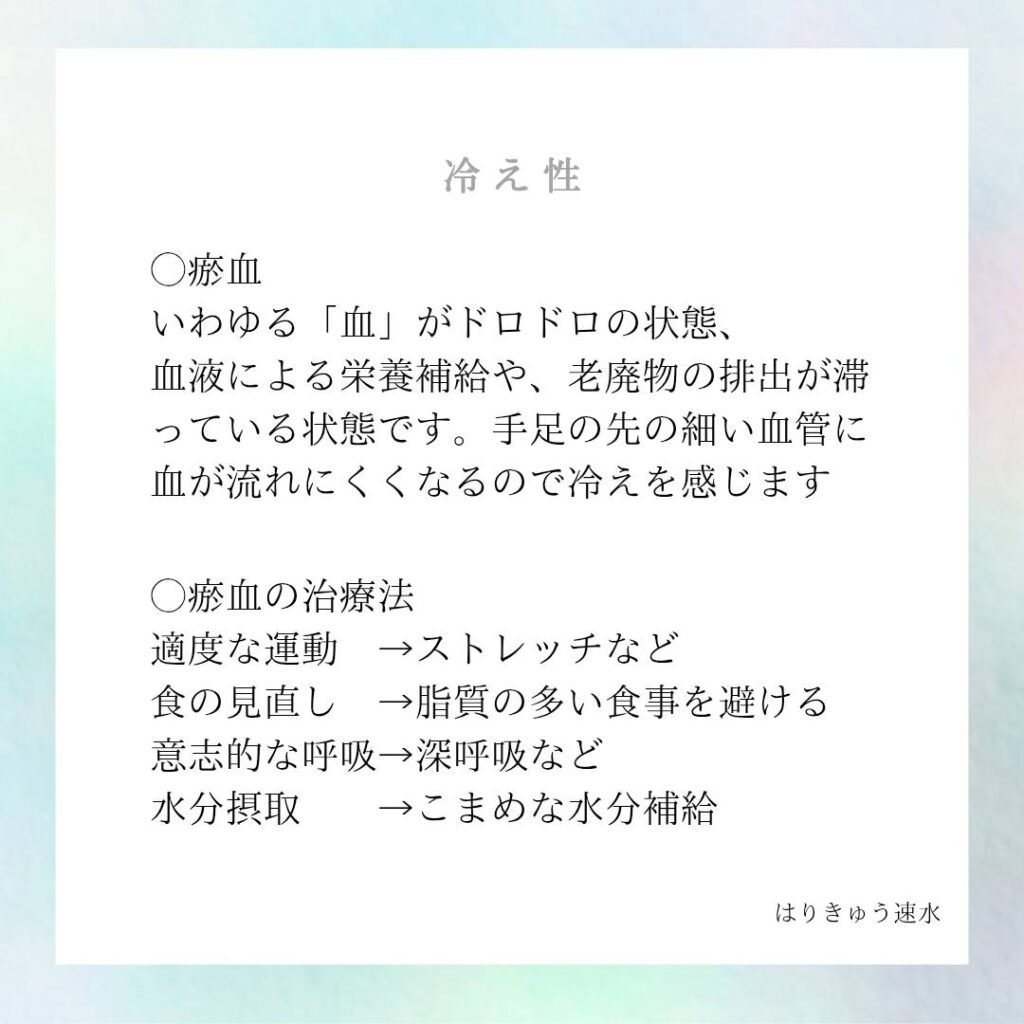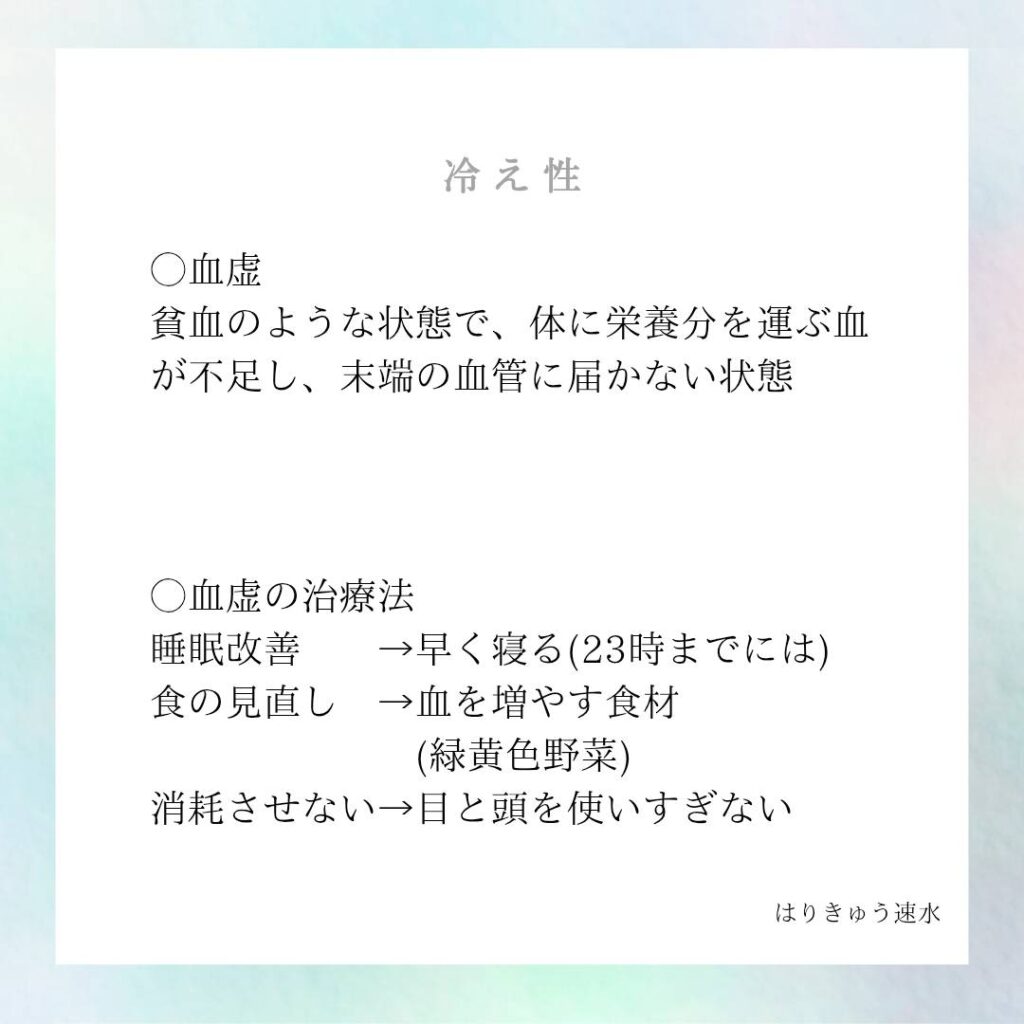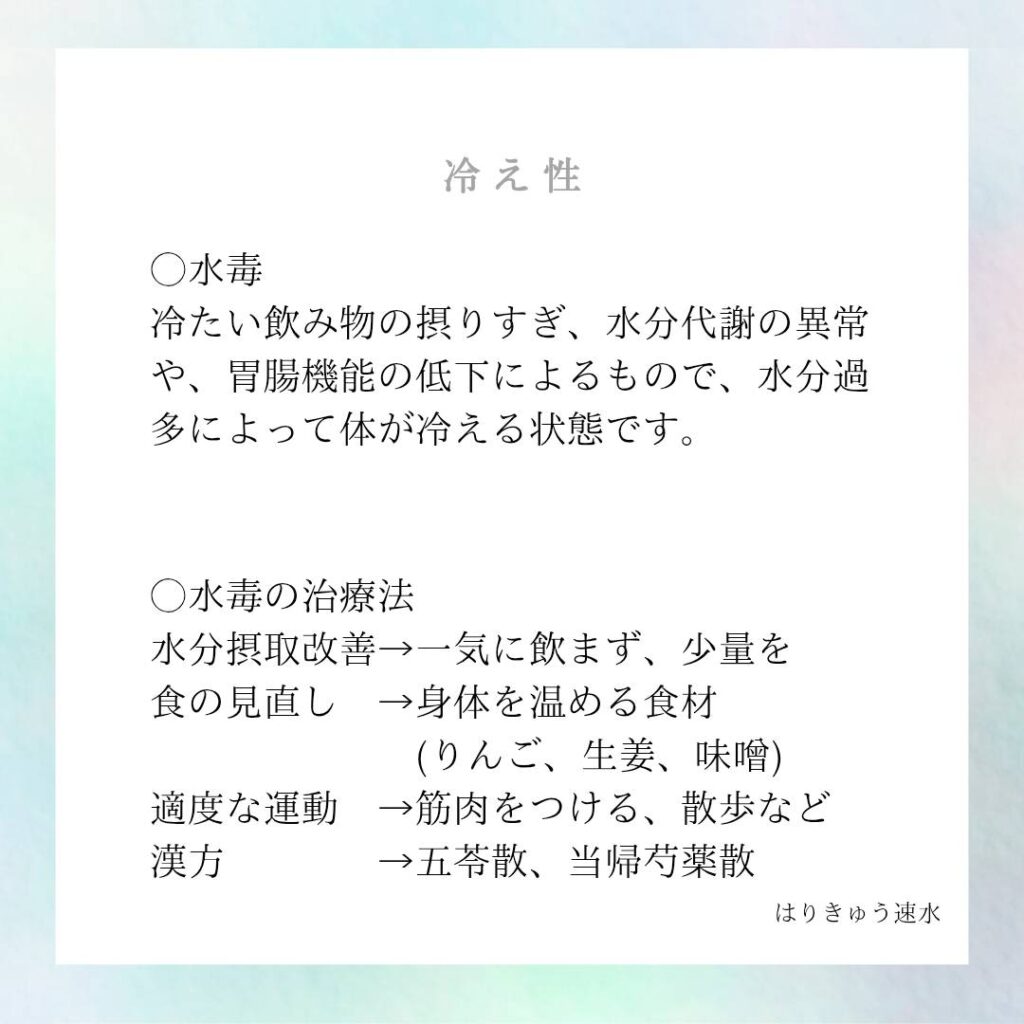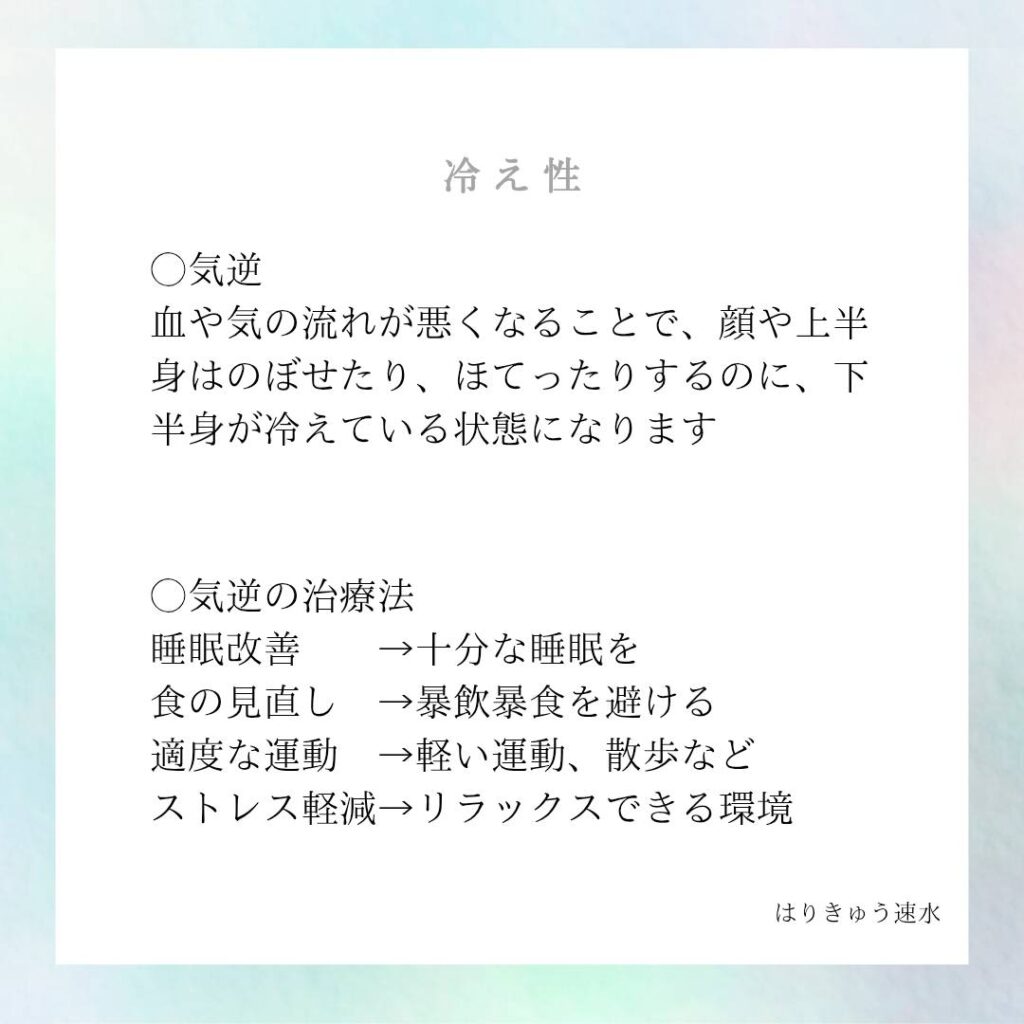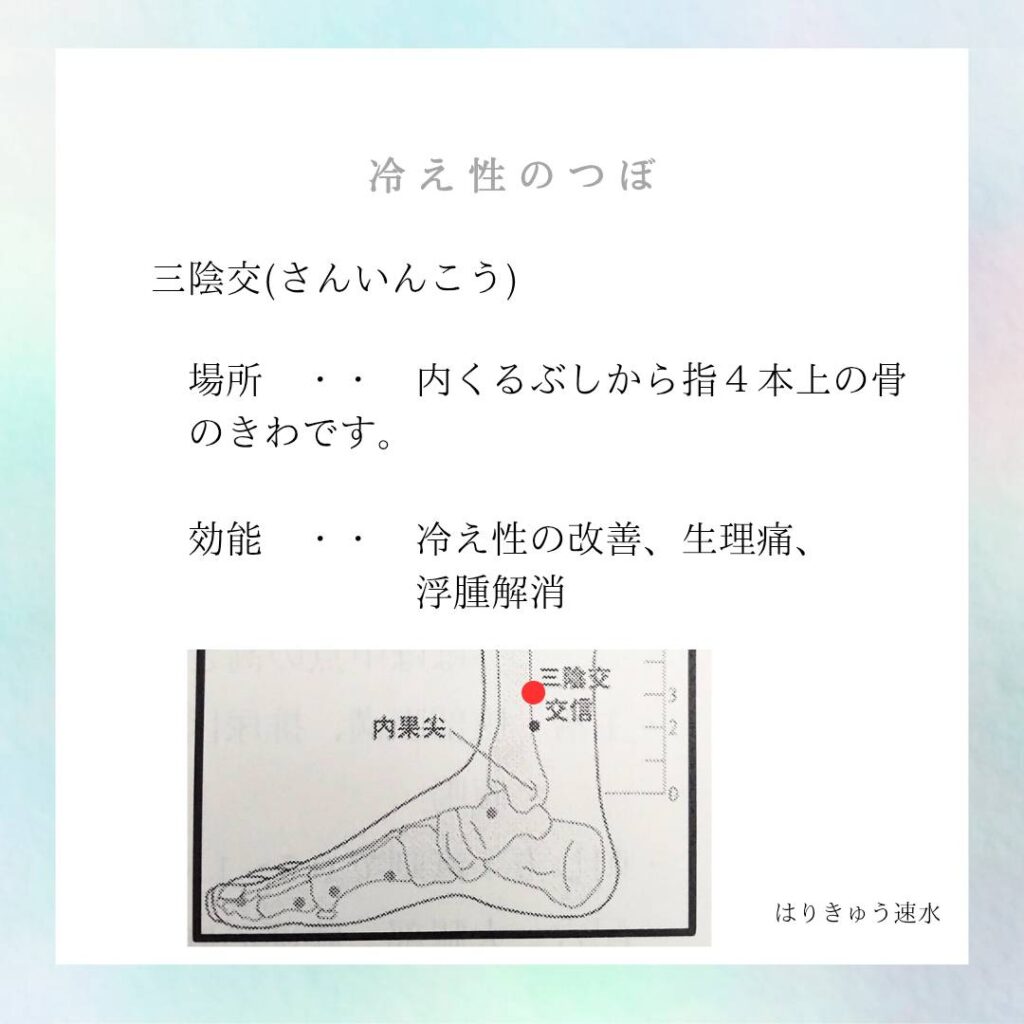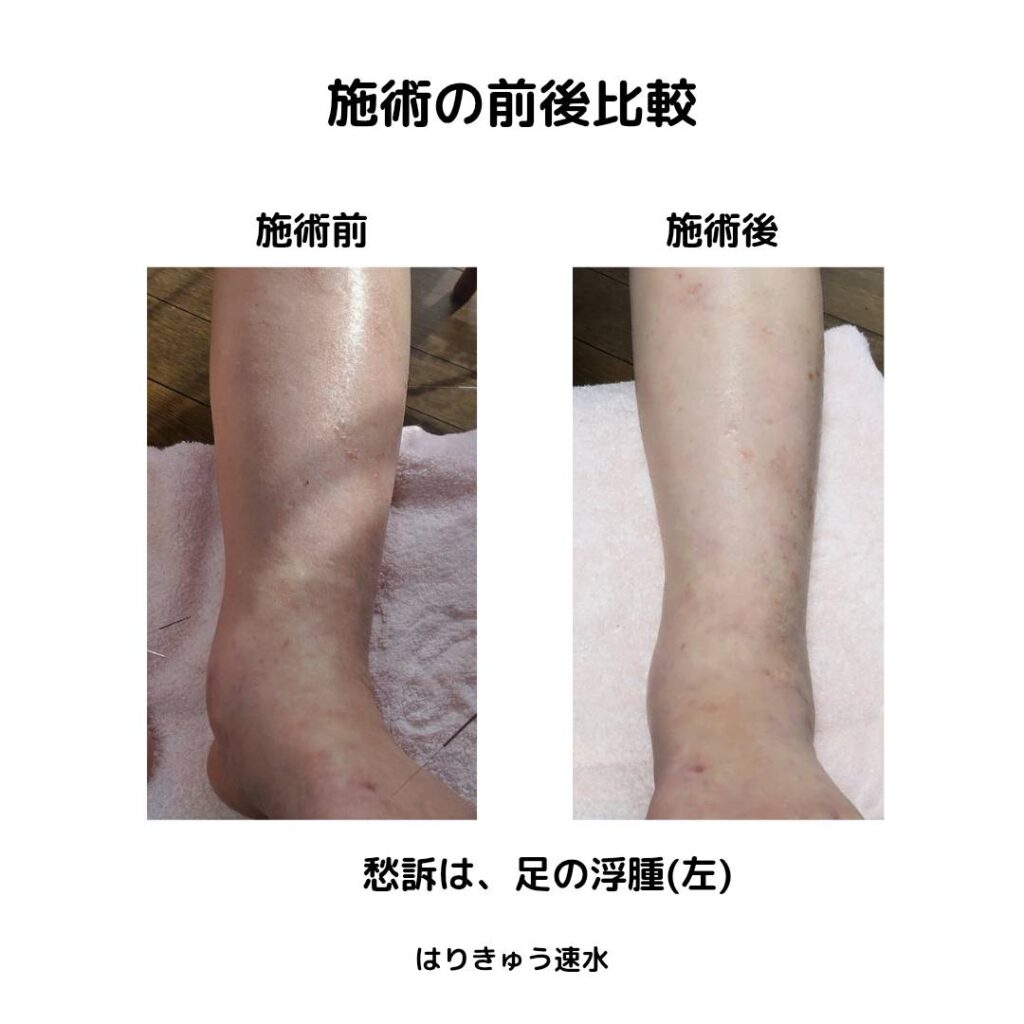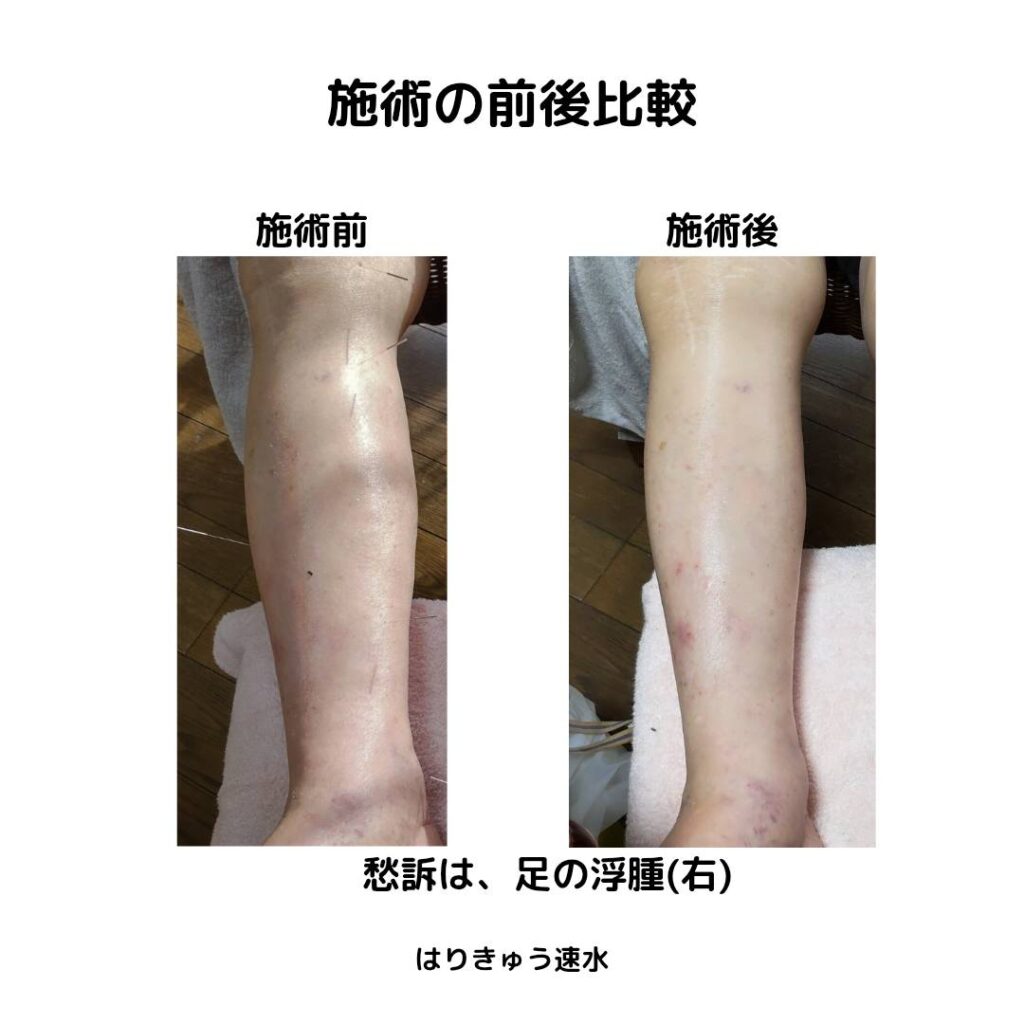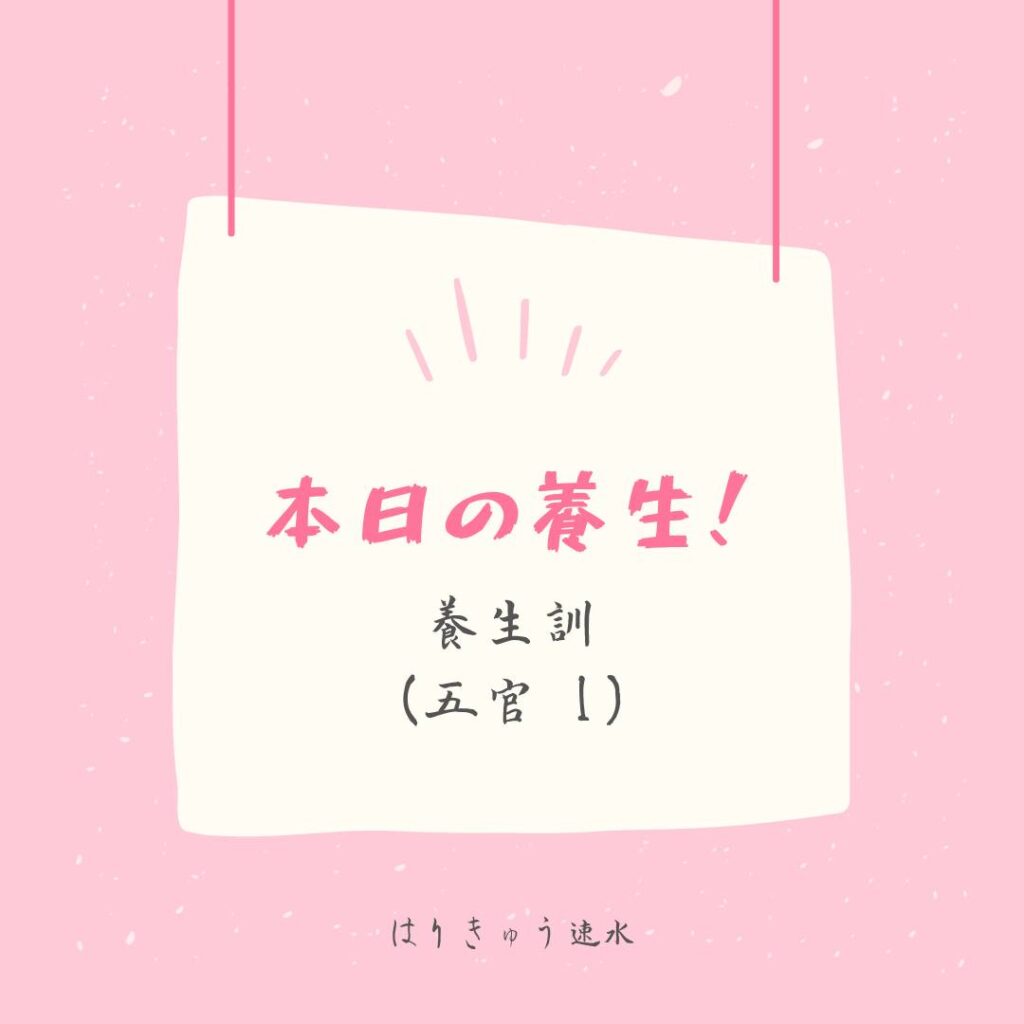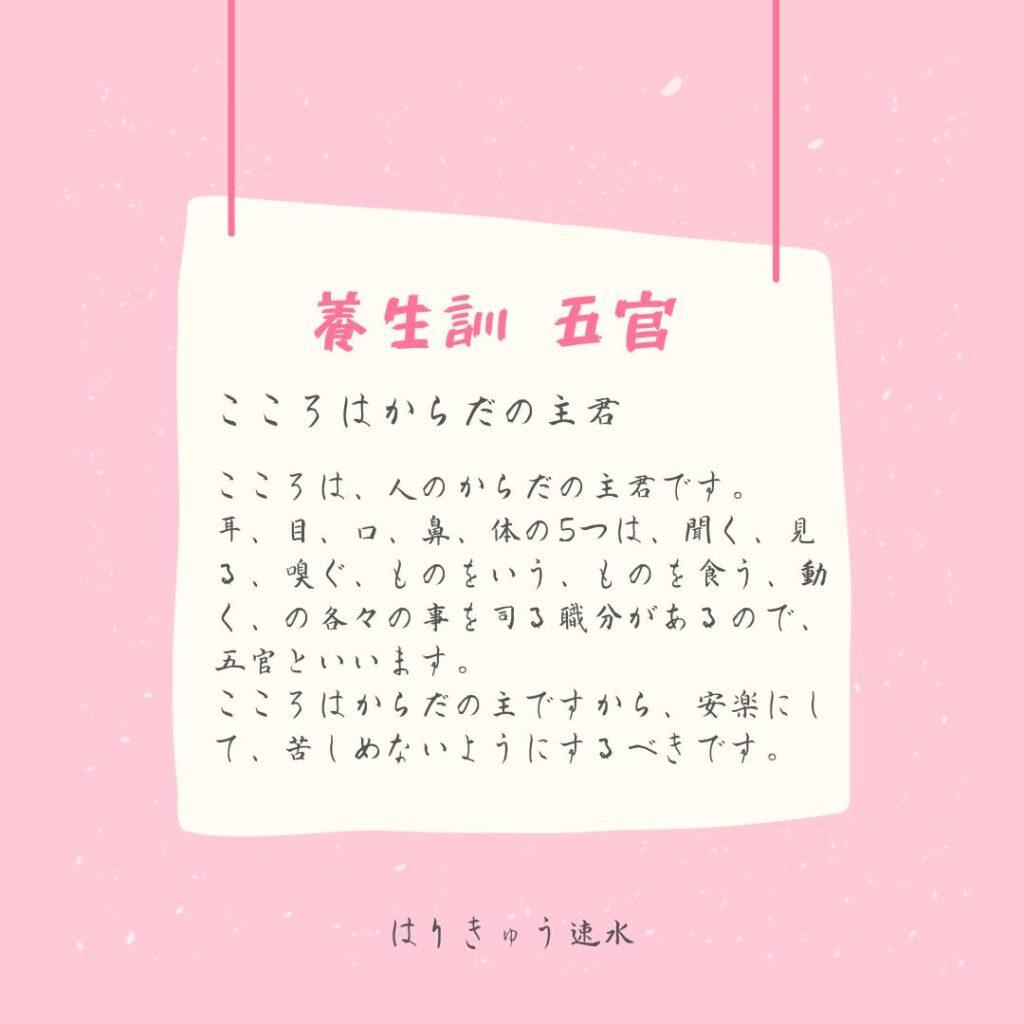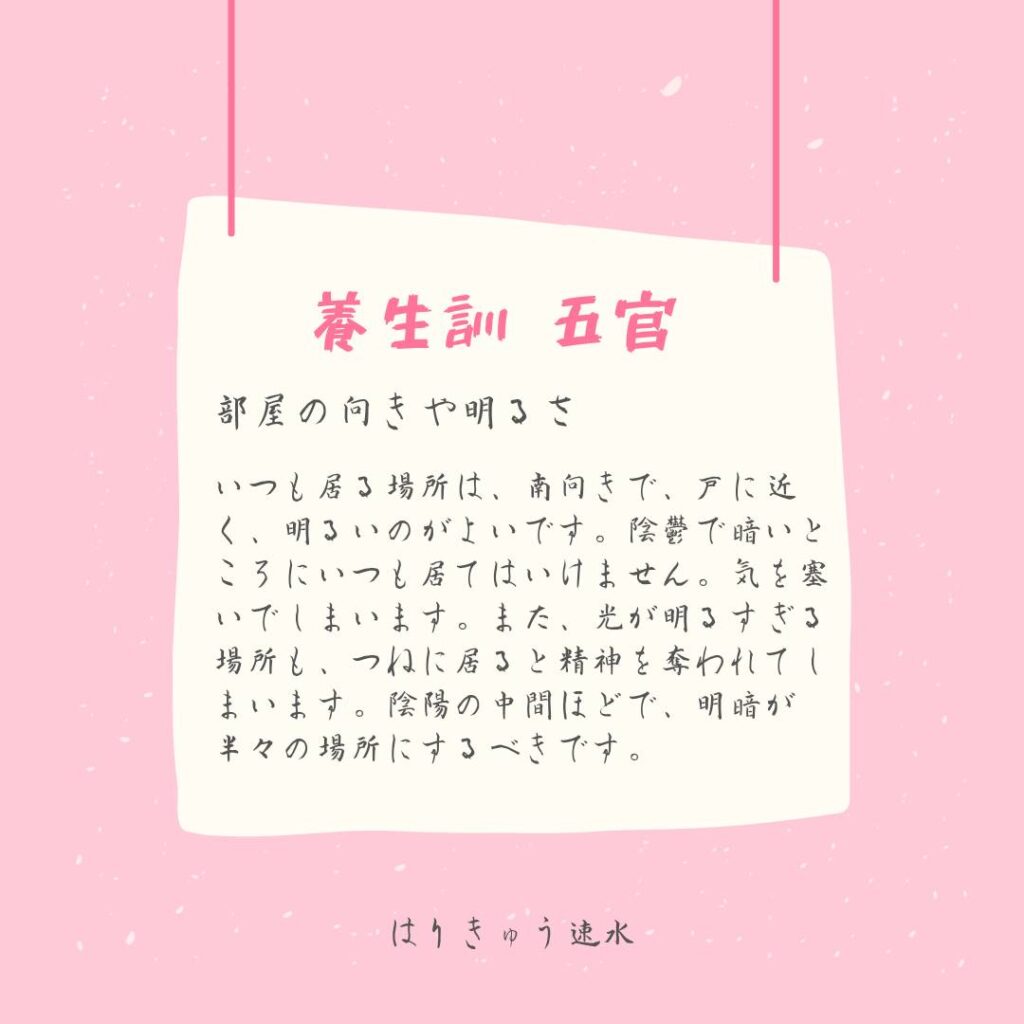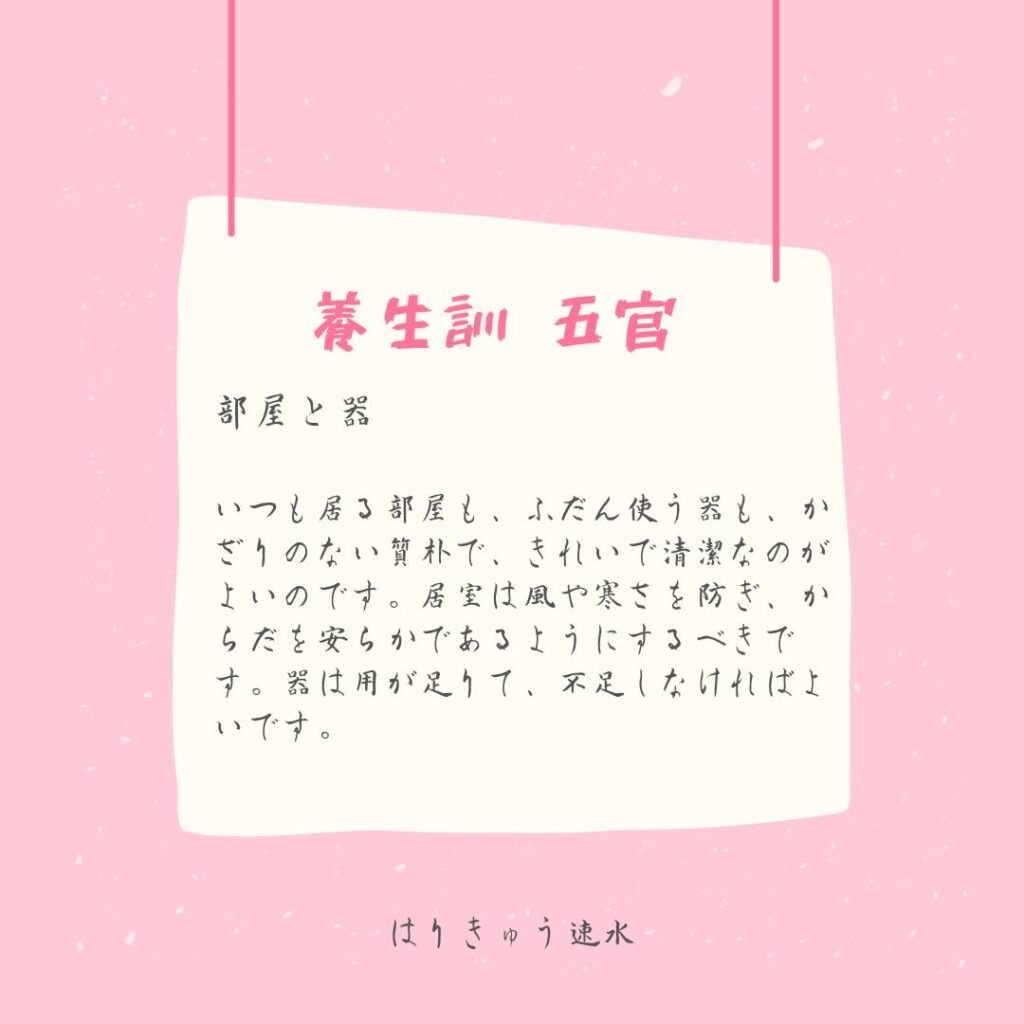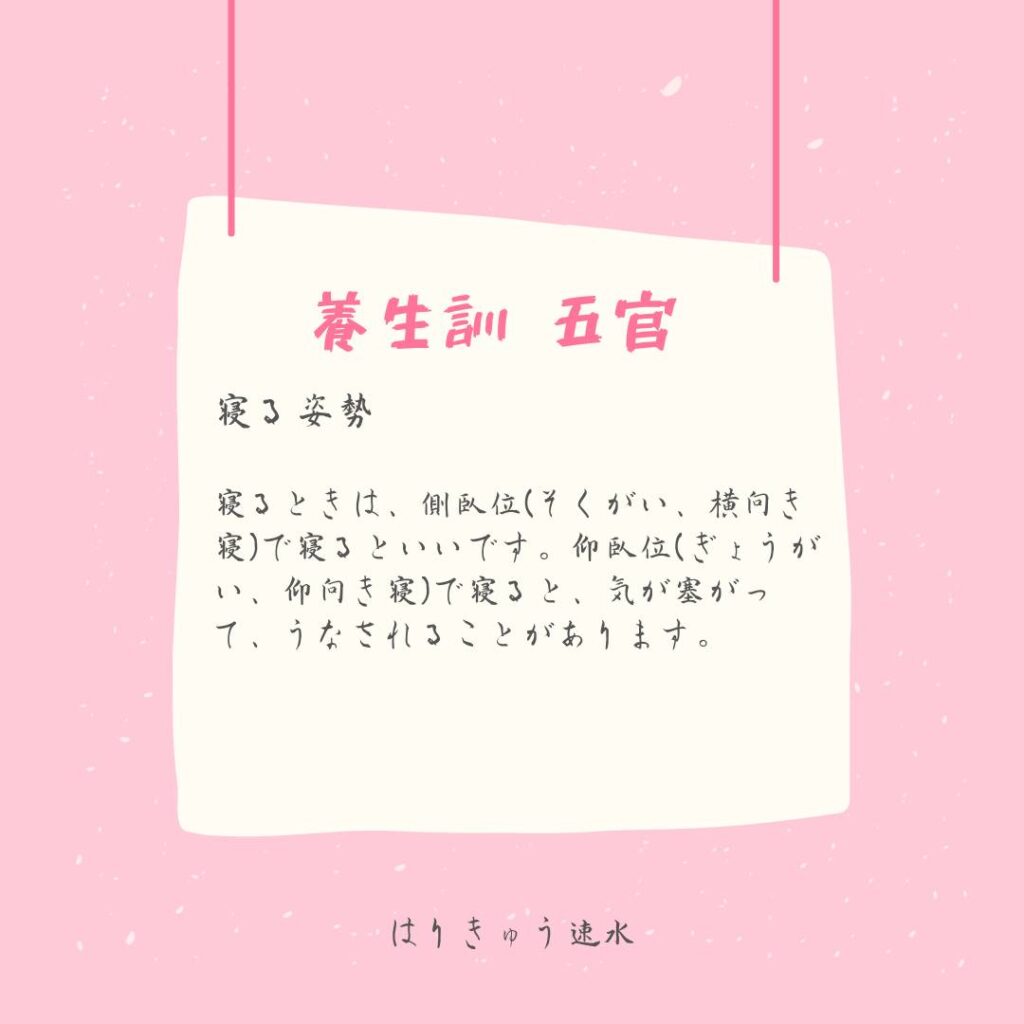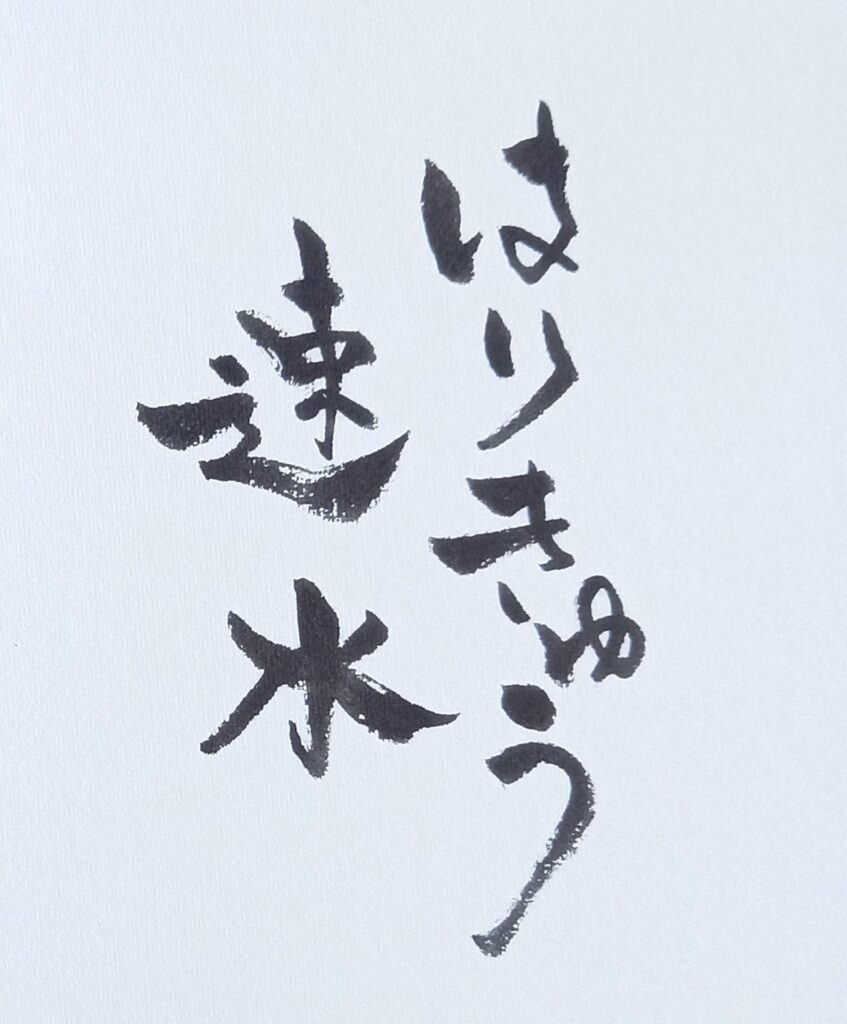こんばんは、はりきゅう速水です
たまには連日になりますがブログ投稿しようと思います。そして、久しぶりの手当て法になります。
さて、今回は、「呼吸器系の病気の手当て②-気管支炎、ぜんそく、肺炎篇」になります
呼吸器系の病気の手当て①は以前投稿しましたが、今回は第2弾になります。仮に該当する症状がある場合は、自分のできることを参考にしてみてはいかがでしょうか
※その前に、「#101手当てするにあたって」を読んでいただくとより分かりやすいです
主に、「 家庭でできる 自然療法 誰でもできる食事と手当法 」から手当法のことを記載しています。ただ、これを必ずやればよいというわけではなく、まずは自分でできることを探してみてください。いきなり手当てや食べ物改善しようとしてもハードルが高く、挫折しやすいと思います(私は、この本を読んで、ためになるなぁと思いつつ、達成するのはむずかしいと思っています)
では、ここからです
① 気管支炎の場合
・急性の気管支炎は、熱とせきと頭痛を伴い、食欲が減ります。熱を下げるには、しいたけとれんこんをいれた玄米スープが良いです。また、ゆきのしたの青汁を飲むのも良いです。胸が痛むときは、からしの湿布を一度だけして、あと芋パスタを貼ると良いです。飲み物としては、玄米茶・番茶・ビワ茶・スギナ茶・食欲がない時はしょうゆ番茶がおすすめです。
・慢性の気管支炎は、熱はでません。のどから気管の方に炎症は浸潤しましょう。のどが腫れたときは、 芋パスタ を巻いておきます。咳が止まらない時でも喉の他に胸に貼るといいです。里芋がない季節の場合は、ジャガイモでも代用可能です。またビワの葉温灸法も効果があります。慢性化したものはいますぐ治るものではないので根気よく続けましょう。
② ぜんそくの場合
・ぜんそくもすぐには治るものではないので、食養法や手当法をつづけるのが治る手立てになると思います。
・手当法:れんこんおろしにしょうがおろしを少々まぜて、塩と黒砂糖少々いれて熱湯をそそぎ、くず湯のようにして一日二~三回飲むとよいです。はげしい場合はれんこんのしぼり汁ばかり盃一杯位飲むとよいです。しょうがの汁を背中にすりこみマッサージするのも良いです。
・食事法:よく噛んで口の中でドロドロにして流し込むような食べ方をしてみましょう。主食は玄米・半つき米・純良の日本そば、副食はふきのとうの佃煮、レンコンと海藻の料理もよいです。
③ 肺炎の場合
・急性肺炎(クループ性肺炎)の場合、急性肺炎は猛烈な高温なので、普段安静にして室内温度を適度にして氷で冷やすのが、まずできることです。ゆきのしたの青汁と豆腐パスタ―を30分おきに取りかえながら解熱を待つのが手当法として記載されています。(緊急性の場合は病院へ)せきどめの手当法としては、大根おろし盃半杯、レンコンおろし盃半杯、生姜おろし小さじ半杯、自然醸造しょうゆ適宣、熱湯一カップ程注いで一日2回飲みましょう。食事はうすあじに調理し、平熱になったらせきどめの手当法はやめて大丈夫です。
・慢性肺炎(カタール性肺炎)の場合、一度だけからしの湿布、その後は豆腐パスタをして、解熱したら芋パスタに切り替えましょう。いずれも胸にします。頭痛の場合は、梅干の果肉をガーゼにのばして額とこめかみにあたるように貼り、油紙をして包帯で巻いておきます。口の渇きは、玄米の重湯か玄米茶に梅干しをいれて飲むと良いでしょう。
・禁食:肉類、赤みの魚、甘味品、刺激物、清涼飲料水、コーヒー、紅茶
今回はここまです。症状がつらいと気持ちも落ち込んだりしやすくなりますので、こつこつできるマインドセットも必要になります。
あくまで、できることを実践してみてください。
「参考文献」
家庭でできる 自然療法 誰でもできる食事と手当法 東城百合子 著
一慧の穀菜食 手当て法 大森一慧 著 大森英櫻 監修
からだの自然治癒力をひきだす食事と手当て 新訂版 大森一慧 著